今回の記事では、『サイコロジー・オブ・マネー』を読んだ感想を書いていきます。
著者はモーガン・ハウセル、訳:児島修です。
全体を通して
具体的な投資手法の解説というよりは、タイトル通りお金に関するマインド面や心理面に関する内容が多かったです。
本書の後に読んだ、JUST KEEP BUYINGはもう少し具体的な内容が多かったように思います。
本書が良かったのは、著者の主観的な主張にとどまらず、具体的なデータやストーリーによって解説されていた点です。
このため、単純な読み物としても楽しめました。
倹約生活や投資が身に付いている人にとっては「当たり前だな」と感じるような内容もありましたが、少し角度を変えた視点で「なるほど」と思う内容もあり、面白かったです。
私のようにある程度投資経験がある人にとっては、自分なりの投資手法が確立されている場合が多いかと思いますので、具体的な投資手法よりもかえってマインド面に着目したような内容の方が楽しめるかもしれませんね。
特に印象に残った箇所について、いくつか書いていきます。
第4章 複利の魔法
氷河期を起こすのは、わずかに涼しい夏
氷河期の原因は、異常気象などで極寒の冬となることが原因ではなく、いつもよりもわずかに涼しい夏が訪れることが原因だそうです。
なぜ涼しい夏が訪れるかと言えば、太陽と月の引力が、地球の公転に数万年に1度影響を及ぼし、地球の浴びる太陽の光量にわずかに影響を与えることが証明されています。
ほんの少し夏が涼しいことで、前年の雪が溶け残る。そうすると残った雪によって、次の年の雪が残りやすくなることで、気温がわずかに下がる。これが繰り返されることによって、氷河期が訪れます。
これは投資の複利でも同じ話で、一見すると非常に小さいと思える影響が、長期的な目線ではとてつもなく大きな力になるということです。
確かに言われてみると、例えば利回り4%を得られたとしても大したことないなと思ってしまいがちですが、これを数十年単位で複利運用すればとんでもない利益が得られるのは、シミュレーションからも分かる通りです。
第6章 テールイベントの絶大な力
全体の1%以下の行動が、投資の成否を決める
この章の内容は、JUST KEEP BUYINGでも触れられていました。
何事においても、半分以上失敗したとしても、わずかな一部分が成功すれば、全体としては成功となるという内容が書かれています。本書では、例としてディズニー映画のエピソードが紹介されていました。ディズニーを成功に導いたのはわずか1/400の作品だそうです。
この話を聞くと、やはりインデックス投資が最強だなと思ってしまいますね。
それでも、しっかり分散していれば個別株投資でも似たような状況は作れると思いますので、私は個別株メインで続けますが笑
第9章 本当の富は見えない
「ウェルス」と「リッチ」はまったくの別物
9章は、わずか7ページですが、倹約生活が身に付いている人にとってはかなり共感できる内容だと思います。
本章では、高級車を乗り回している人のエピソードが書かれています。
人は、目に見えるものから誰かの豊かさを判断しようとしますが、口座残高をはじめとする実際の中身は分かりません。
面白いと思ったのは、「10万ドルの高級車を持つ者は裕福であると思われるかもしれないが、実際には、高級車を買う前よりも手持ちが10万ドル減っているだけ」という表現です。
なるほど確かに、言われてみれば車の資産価値を無視した場合、ただ借金を抱えているだけとも考えられますね。
そういう意味では、高級品を身に付けているほうがむしろ、「私は無駄遣いをしています」「総資産としては大して持っていません」と言っているようなものかもしれませんね。もちろん真の金持ちの場合は別ですが。
しかし、「金持ちほど衣服はユニクロで済ます」などの言説に通ずる部分があるかと思います。
第17章 悲観主義の誘惑
あなたも私も、悲観論が大好き
17章では、悲観論は楽観論よりも賢く、もっともらしく聞こえるということが書かれています。
面白いと思ったのは、先の大戦後の日本のことが書いてあったことです。
もしも敗戦後に、日本の学者が次の主張をした場合、いったい誰が信じるか?という話です。
「国民よ、元気を出せ。我々が生きている間に、日本経済は終戦前の約15倍の規模に成長する。平均寿命は約2倍になり、株式市場は史上空前の収益を上げるはずだ」
こうして文字にしてみると、確かにあり得ないなどと思ってしまいますね笑
ただ、最近の話で思い返せばコロナショックもそうでした。
あのタイミングにパンデミックが起きるなんて予想できなかったし、日常生活に戻っていく中で様々なことがありました。株価についても、非常に大きなボラティリティとなりました。
今後必ず株価の調整局面が訪れるかと思いますが、悲観論に流され過ぎないように常に頭の片隅に入れておきたいですね。
まとめ
本記事では、モーガン・ハウセル著『サイコロジー・オブ・マネー』の感想と、特に印象に残った箇所をご紹介しました。
本書は具体的な投資手法を解説する本というよりは、豊富なデータやストーリーを通して、お金と長く付き合うためのマインド面を学べる一冊です。
今回取り上げた「複利の魔法」や「本当の富は見えない」、「悲観主義の誘惑」といったエピソードから共通して言えるのは、短期的な視点や目に見えるものに惑わされず、長期的な視点を持ち続けることの重要性であると思います。
投資初心者の方には、お金と向き合う上での普遍的な哲学を知る入門書として、そして投資経験者の方には、自身の投資スタイルを再確認し、思考を深めるための良書としておすすめできる一冊です。
ただ、本書を読めば自分の投資スタイルや考えがガラッと変わるというものではないと感じました。あくまでも補足的、補強的な捉え方をすると役に立つと思います。
また、著者はあくまでインデックス投資を勧めていますので、個別株投資家にとっては対立する意見もあるかもしれません。
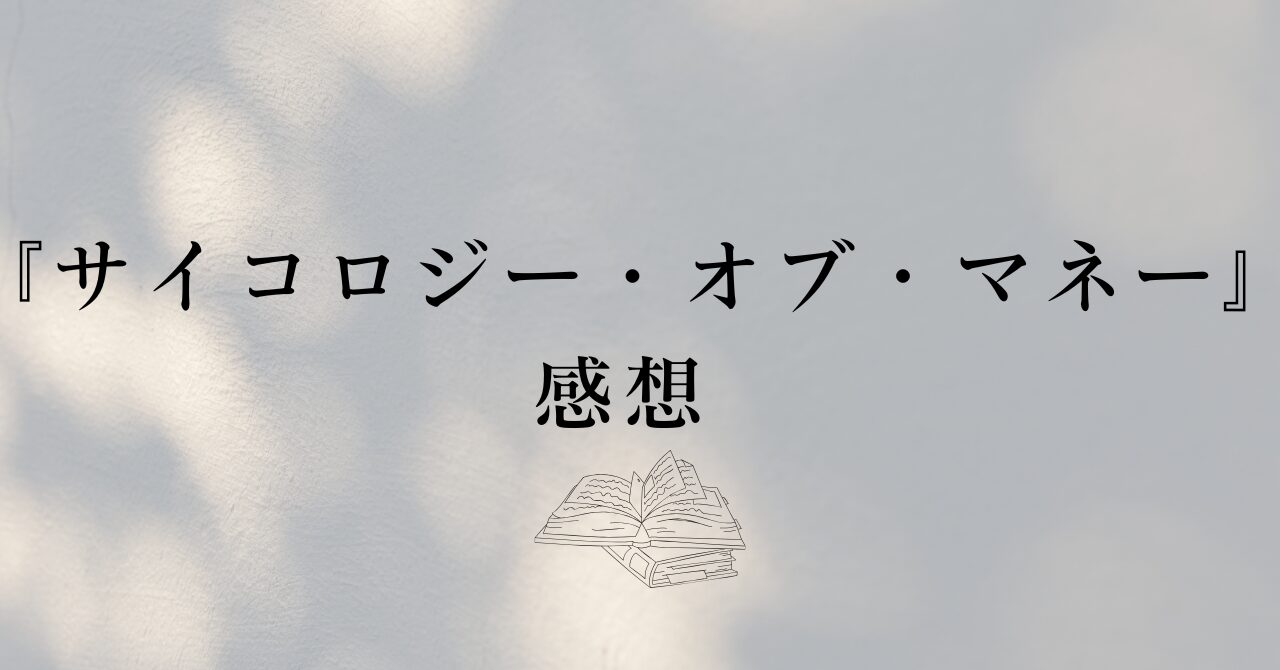

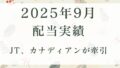
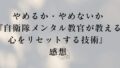
コメント